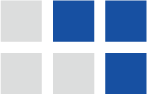【ライティング編】Proユーザー勉強会レポート
公開日: 2025年10月06日
今回の勉強会では、日々の情報発信やコンテンツ制作を劇的に効率化する、多彩なAI搭載ツール群について、開発者である中野巧が解説しました。本レポートでは、文章作成から画像生成、マーケティングまで、多岐にわたるツールの機能と具体的な活用法を分かりやすくまとめます。
なお、本勉強会のアーカイブ動画や要約レポートは、プロプラン会員限定コンテンツページにて順次公開されます。リアルタイムで参加できなかった方も、そちらで内容をご確認いただけます。
3つの重要ポイント
【ポイント1】目的に合わせてAIツールを使い分ける
投稿のテーマ探しには「Topicky」、SNSの短い文章なら「Socialy」、ある程度まとまった文章なら「Empathy」というように、作りたいものに合わせて最適なAIツールを選ぶのがコツです。多種多様なツールを使い分けることで、あらゆるコンテンツ制作が驚くほどスムーズになります。
【ポイント2】AIは「ゼロからイチ」を生み出す最強の相棒
何を書けばいいか全く思いつかない時こそ、AIの出番です。AIにアイデアのタネを出してもらうことで、最も大変な「ゼロからイチ」の部分を乗り越えられます。白紙の状態から悩む時間を大幅に減らせます。
【ポイント3】AIの文章に「自分らしさ」を加えて完成させる
AIが作った文章はあくまで下書きです。そのまま使わず、最後に自分の言葉や表現、人間味あふれる「色気」を加えることが重要です。この一手間が、読者の心に響くオリジナルコンテンツを生み出す秘訣です。
無料で使える!
業務効率を加速させる便利ツール群
まずは、誰でも無料で利用できる便利なツール群が紹介されました。それぞれのツールの特徴と主な用途は以下の通りです。
Diffy:文章の差分を瞬時にチェック
2つのテキストを比較し、どこが変更されたかをハイライト表示するツール。AIが生成した文章の修正箇所や、チームでの共同編集時の変更点を一目で確認したい場合に非常に役立ちます。
Wordy:語彙を広げる類語・連想語検索
あるキーワードを入力すると、その意味に加えて類語・連想語・対義語を一覧で表示してくれます。「いつも同じ表現になってしまう」といった悩みを解決し、より表現力豊かな文章を作成するためのヒントが得られます。
Maily:スプレッドシートで簡単メルマガ配信
Googleスプレッドシートと連携させることで、専門的なメルマガスタンドを契約することなくメールの一斉配信が可能になるツール。小規模なイベントの告知やリマインドメールなど、手軽に配信したい場面で活躍します。(※Googleの仕様変更により、1日の送信上限は約100件となっています)
Catchy:キャッチコピーのアイデアが無限に湧き出す
ボタンを押すだけで、「定番」「インパクト」「個性的」という3つのカテゴリでキャッチコピーのアイデアを次々と生成します。詳細画面では、各コピーの解説や問いかけも表示され、発想を深めるきっかけを与えてくれます。
Kindly:Kindle出版のコンセプト作りを強力サポート
「売りたい商品」または「書きたい内容」からスタートし、ターゲット読者や読者の悩み、読後にもたらされる未来などをAIとの対話形式で明確にしていくツール。最終的に、本のコンセプトと仮タイトル案を複数提示してくれます。
Pixy:Webサイトに最適!高品質な画像圧縮ツール
Webサイトの表示速度を低下させる重い画像を、画質をほとんど劣化させることなく軽量化できるツールです。スライダーを動かすだけで圧縮率を調整でき、ユーザー体験の向上に貢献します。
Snappy:画像の背景を簡単切り抜き&微調整
アップロードした画像の背景をAIが自動で認識し、きれいに切り抜いてくれます。切り抜き後に、ブラシツールで消しすぎた部分を復元したり、残したい部分を微調整したりすることも可能です。
Linky:長いAmazonリンクをスマートに短縮
ECサイトの長い商品URL、特に日本語が含まれる複雑なAmazonのリンクを、スパムと誤解されないクリーンで短い公式URLに一瞬で変換します。
QRcody:URLからQRコードを即時生成
任意のURLを入力するだけで、瞬時にQRコードを生成できるシンプルなツールです。ダウンロード形式はPNGとSVGから選択でき、印刷物にも対応可能な高解像度で保存できます。
【実践編】
AIライティングツールの徹底活用法
セミナーの後半では、より高度な文章作成を支援するプロプランの主力ツールについて、実演を交えながら解説が行われました。
Imagy:一瞬で高品質な画像生成プロンプトを作成
「高校時代」といった短いキーワードから、「夕焼けが差し込む放課後の教室」といった情景が目に浮かぶような、具体的で高品質な画像生成プロンプト(指示文)を日本語と英語で自動生成します。AIは英語で思考するため、質の高い画像を生成するには英語のプロンプトが有効であり、このツールはその手間を大幅に削減します。
Topicky:もうネタに困らない!配信テーマ発見ツール
既存のブログ記事やメルマガ、あるいは単一のキーワード(例:「りんご」)を入力するだけで、指定したターゲット読者に響く配信ネタを「ひらめきネタ(独自性のある切り口)」と「鉄板ネタ(王道の切り口)」の2種類で提案してくれます。さらに、各テーマの書き出し文や、タイトルを「初心者向け」「より具体的に」といった形で深掘りする機能もあり、ネタ切れの悩みを根本から解消します。
Socialy:SNS投稿を手軽に作成する5つのステップ
エンパシーライティングのフレームワークを基に、5つのシンプルな質問(「投稿のテーマ」「伝えたい一言」「きっかけ」など)に答えるだけで、AIが共感を呼ぶSNS投稿文を自動で作成します。ハッシュタグの提案や、投稿内容に合わせた画像生成プロンプトの作成機能も搭載しており、SNS運用をトータルでサポートします。
Empathy:AIとの共創で「伝わる」長文コンテンツを作成
単に文章を自動生成するだけでなく、AIとの対話を通じて書き手の思考を整理し、オリジナリティの高い長文コンテンツ(ブログ、メルマガなど)を作り上げるためのツールです。読者のポジティブな反応(共感)とネガティブな反応(反発)を両面から想定し、それぞれに対応するメッセージを組み立てていくプロセスが特徴です。最終的に、入力したメッセージ要素をAIが最適な順番に並べ替え、一貫性のある感動的な文章のドラフトを生成します。
質疑応答と
AIとの向き合い方
AIは「壁打ち相手」、最終的な仕上げは自分で
「開発者自身はAIライティングツールをどう使っているのか?」という質問に対し、中野氏は「ネタ出しや切り口のヒント、構成案のたたき台として活用するが、最終的には自分の言葉で書き直すことが多い」と回答。AIが生成した文章は、完成度が高くても人間味や「色気」に欠けることがあるため、AIとのキャッチボールを通じて得た素材を元に、最後に自分のエッセンスを加えることが、読者の心に響く文章の鍵であると述べました。
「AIに使われる」のではなく「AIを使いこなす」
AIはあくまで道具であり、万能ではありません。自分でやった方が早い簡単な修正までAIにやらせようとすると、かえって時間がかかることもあります。「ゼロからイチを生み出す」という最も困難な部分をAIに任せ、そこから先の展開や微調整は自分で行う。この「AIとの共創」というスタンスが、AIを最大限に活用する秘訣です。
まとめと次回予告
本勉強会では、AIを単なる「自動化ツール」としてではなく、自らの創造性を拡張するための「優秀なパートナー」として活用するための具体的な方法が数多く提示されました。参加者からは、「自分のアイデアの原液を投入することで、完成度の高いドラフトが作れる」「いつもつまずいていた最初の部分の救世主になりそう」といった感想が寄せられ、AIとの新しい付き合い方の可能性を大いに感じさせる時間となりました。
次回は、専門知識がなくても短時間で効果的なランディングページを作成できるツールを中心に解説が行われる予定です。
参加者の声
「ひらめきのネタが素晴らしすぎる!」
`Topicy`が特に印象的でした。送信済みの自分のメルマガを元に、新しい「ひらめきネタ」を提案してもらえたのは大きな発見です。ラフ案作成後に`Topicy`で磨きをかける、といった使い方もできそうで、ネタ出しが楽しくなりそうです!
「0→1でつまずく部分の救世主です」
自分の中にアイデアの「原液」はあっても、それを形にする最初のステップでいつもつまずいていました。AIに骨組みを作ってもらい、完成度の高いドラフトを元に最後に自分らしさを加えて磨き上げる、という流れで使えると感じました。
「英語プロンプトで、いい感じの画像になりました」
画像生成ツールはもう手放せません。特に、`Imagy`で英語のプロンプトを作ってもらったら、質の高い画像が生成できて驚きました。42年前の写真を現代風にするなど、発想次第で色々試せるのが面白いです。
「移動時間でもアイデア出しができそう」
各ツールがとても使いやすく、スマホ(Apple Pencilでも操作できました!)からでも直感的に使えそうです。これなら移動中のような短い時間でも、手軽にアイデアを練ったり文章を作成したりできそうだと感じました。
「AIとキャッチボールする、という使い方が腑に落ちました」
開発者の中野さんご自身が、AIをヒント出しや壁打ち相手として活用していると伺って安心しました。AIに全てを任せるのではなく、あくまで「共創」のパートナーとして付き合う。このスタンスが、ツールを使いこなす上で最も重要だと理解できました。
Proプランにご興味をお持ちのあなたへ
レポートで紹介したツールは、主にProプラン会員限定です。
まずは無料ツールで使い心地を体験いただき、Proプラン募集の優先案内へご登録ください。